|
2008年9月6日(土)に第12回KIT読書会が開催された。
課題本は、「千年、働いてきました――老舗企業大国ニッポン」である。KIT読書会については、第5回「The war for talent(人材育成競争)」を紹介している。
第6回以降の読書会の活動を以下に記録しておきたい。
第6回:2007年4月21日(土)「人を動かす(ディール・カーネギー、創元社)」
第7回: 6月30日(土)「ウェブ進化論(梅田 望夫、ちくま新書)
第8回: 8月25日(土)「最高のリーダー、マネージャーがいつも考えている
たったひとつのこと
(マーカス バッキンガム、日本経済新聞社)」
第9回: 12月22日(土)「 同上 」
第10回:2008年3月22日(土)「地頭力を鍛える 問題解決に活かす「フェルミ
推定」(細谷 功、東洋経済新聞社)」
第11回: 6月21日(土)「起死回生のターンアラウンド
(内海 康文、東洋経済新聞社)」
今回の読書会のファシリテーターである“廣瀬かよさん”から事前に送付されてきた議論のポイントは、以下のとおりである。
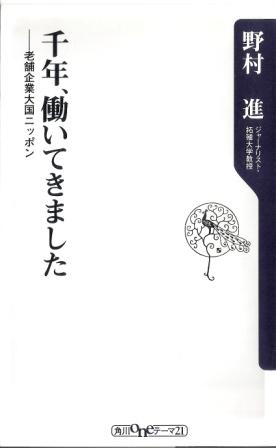 1) 日本に老舗企業が多い理由 1) 日本に老舗企業が多い理由
本書で指摘されているポイントを整理した上で、賛否、他に無いのか?等考えてみましょう。
2) 老舗が老舗たり得た理由老舗企業達はなぜ長年生き残ってこられたのか?
本書で指摘されているポイントを整理した上で、賛否、他に無いのか?等考えてみましょう。
3) 現時点での新興/中小企業の"生きる道"とは?
どんな老舗も最初は「ベンチャー企業」老舗企業の歩んできた道から導き出される普遍性とは?
KIT読書会では、ファシリテーターが毎回持ち回りで事前に論点を送付する。この論点に対して参加者の経験や知見を元に話し合うのだが、毎回、新しい発見がある。
まさにKIT(大学院教育)の売り物であるポートフォーリオが、自分以外の人たちからのリフレクションによって新しい自分の考え方が形成・創造され、昇華されるという過程を、卒業後も経験・体験できる貴重な場となっている。
話題を変えよう。
この読書会の終了時に次回の課題本を話し合った。参加者のお一人である“鈴木健”さんから『三本の矢』(榊東行氏、早川書房)を紹介された。
今日(10月11日)、この上巻を読み終えたので、第三部 衝撃の巻頭に以下の引用を紹介したい。
<1997年デンヴァー・サミット前後の各国首脳語録>
・現在の米国経済は最も健全で世界最強だ。・・・・すべての国が(市場主導の民主主義を実現した)米国と同じ選択をすべきだ。(ビル・クリントン)
・今回アメリカは世界最強の経済に復活し、その経済モデルを他国に伝える番になった。(ロバート・ルービン)
・弱者を切り捨てる市場経済と、機会の平等、自由、個人の基本的人権に根ざす民主主義は突き詰めると相容れない。(ジャック・アタリ)
・随分と(アメリカは)自信を持っているようだが、我々は、アメリカのモデルを採用すべきではない。すべとの国には独自のモデルがある。(ジャック・シラク)
・アメリカは、貧富の差の拡大を助長するなど問題も多い。(ドミニック・ストロカーン)
この本の論点を書き出しておきたい。
<日本における官僚の肥大化について>
過去に多くの緊急事態が起こり、そのたびに緊急対策が関係省庁によって作成されてきた。ニクソンショック、第一次・第二次石油ショック・・・、そして最近では、湾岸戦争、証券不祥事、阪神大震災など。過去の緊急対策は、関係省庁にとって絶好の権限拡大の場になっていた。人手や予算が足りなかったから事態を未然に防げなかった――という理屈で、各省庁は文字どおり「焼け太り」をしてきた。
 石油ショックの後、通産省は、石油備蓄や新エネルギー開発のための多額の予算を手にした。天安門事件や湾岸戦争で情報をまったく集められなかった外務省は、情報関連の予算や組織の定員増を獲得することに成功した。証券不祥事の際に設けられた証券取引等監視委員会は、大蔵省の証券行政に関する権限や機構をさらに拡大した。 石油ショックの後、通産省は、石油備蓄や新エネルギー開発のための多額の予算を手にした。天安門事件や湾岸戦争で情報をまったく集められなかった外務省は、情報関連の予算や組織の定員増を獲得することに成功した。証券不祥事の際に設けられた証券取引等監視委員会は、大蔵省の証券行政に関する権限や機構をさらに拡大した。
<世論は『合理的であるゆえに無知(rationally ignorant)』である>
賢い国民は小さな村の村長選でもないかぎり、自分の一票が選挙結果を左右することなどあり得ないことを知っている。実際に一票差で決まった国政選挙などは今までにない。だとすれば、政治に興味を持って、新聞の政治面を読んだり、時間を費やしてまじめに投票所に行くのは、賢い国民にとって、合理的な選択ではない。どうせ選挙結果に自分の一票がなんらの影響も与えないならば、誰に投票するかを決めるために政治経済のことを考えたり勉強したりするよりも、自分の仕事や家族サービスにでも集中するほうがずっと合理的ということになる。
そのため、合理的な国民――より幅広くは世論――は、政治経済に無知ということになる。
<政治学者と経済学者>
同じ政治経済現象を扱っても、典型的な政治学者と経済学者とでは、個人の意思決定能力への理解が根本的に異なる。多くの政治学者が経験則的(帰納的)観点から、個人や世論の無知さを強調するのに対し、経済学者は個人の合理性を前提として演繹的に理論を構築する。
『無知』対『合理性』。その両者の理解の橋渡しをする論理が、『合理的であるがゆえに無知』という理屈なのである。一票差で決まる選挙などあり得ない以上、いくら民主主義といっても、一票しか持たない各個人は政治に完全に無力だ、という考えがこの理屈のスタートポイントである。
ハミルトン、マディソンといったアメリカ建国時の思想的リーダーたちの手による、そして、十九世紀前半にアメリカに滞在した若きフランス人トクビルが著したは、彼らが危惧した<多数者による専制>は、奇しくも、制定当時最も民主的といわれたワイマール憲法下のドイツで、ナチスの手によって実現した。
こういう民主主義への強い懐疑心は、リップマン、キー、コンヴァース、ミラーといった二十世紀の代表的なアメリカ政治学者によって引き継がれた。彼らは、民主主義の依って立つ世論に着目し、それがいかに無知で非理性的で、扇動乗せられやすいかを、数々のデータを駆使して統計学的に実証した。
の筆者たちや、その当時の代表的なリベラリストで後に大統領になるジェファーソンでさえも、立法府の優位から行政府の独立性をいかに担保するかに腐心している。民衆の意思形成に懐疑的だったトクビルは、行政エリートの独立性の重要性と、その果たすべき役割の大きさを強調した。
アメリカの政治学者のなかに、強力な日本の官僚制を評価する人が多い背景には、こうやって積み重ねられてきた民主主義の欠点に関する考察と、それをサポートする膨大な量の実証データの積み重ねがあるためである。こういう過去の蓄積を弁えれば、日本の一部の政治家やジャーナリストが唱える「民主主義の観点から言って、官僚制はかくあるべき、云々」といった議論が、いかに稚拙なものであるかが分かる。
民主主義のメッカであるアメリカでそんなことを主張すれば一笑に付されるだけだ。要は、民主主義は絶対ではなく、欠陥だらけなのだ。従って、「民主主義のためにはⅩが必要」などという議論ではなく、民主主義の欠落を補うような社会経済的にすぐれたシステムをいかに構築するか、という議論こそがなされなければならない――。
<日本の官僚>
果たして日本の官僚は、政治から独立して、国家にとっての理想を追求してきたであろうか?民主主義制度化にあって望まれる行政府としての役割を日本の官僚制度は果たしてきたのであろうか?
多くの場合、官僚は独立性を捨てて政治や財界に近づき、自らの利益のために彼らと取引をしてきた。政治家には、<票とカネ>に結びつく一~二割の行政領域を差し出し、残りの八~九割を自分の思うままに操る。産業界には、自省からの天下り人員に応じた発注や補助金を割り振ってきた。
もし行政府の独立が望ましいとしても、それを自ら断ってきたのが、日本の官僚なのではないか。立法府からの独立どころか、自ら政治に近づき、政治や世論を操作することによって、自分たちの思うような国を動かそうという野心までも抱くようになったのではないか?
<望ましい考え方>
世論を代表する立法府と、計画性・継続性・理知性が必要な行政府とが、相互に独立し相互に抑制しつつ、微妙に均衡する状態なのであろう。そういう状態において、立法府は世論の動向をくみ取り、行政府は社会全体の利益が何かを論理的に追求することが、二者の理念的な関係のはずである。
ここからは、私の主観も含めて記録しておきたい。
近代経済学がアメリカにおいて発展してきたということは、この国の風土や文化、歴史など(コンテキスト)が、時代の要請によって培われ、醸成されたためであり、ノーベル経済学賞(アメリカが受賞者の過半を占める唯一の部門)の受賞者が、アメリカが断トツ(39人)、二位はイギリス?8人ということからも、窺える。
ノーベル賞といえば、自然科学分野や平和賞と思っていたが、経済学の分野があることを改めて認識した次第である。また、筆者が紹介してくれた民主主義のバイブル本「Democracy in America(トクヴィル)」をいつか読んでみたいと思った。
この本の一節に、以下の『諸国民の福利にとっては、治者が徳と才能を持っていることが重要である。けれども治者にとっておそらくなおいっそう重要なことは、治者が被治者大衆に反する利益をもたないということである。なぜならば、治者が、被治者大衆に反する利益をもっている場合は、徳はほとんど無用なものとなるかも知れないし、才能も有害なものになりかねないからである。(井伊玄太郎訳)』
(つづく)
|